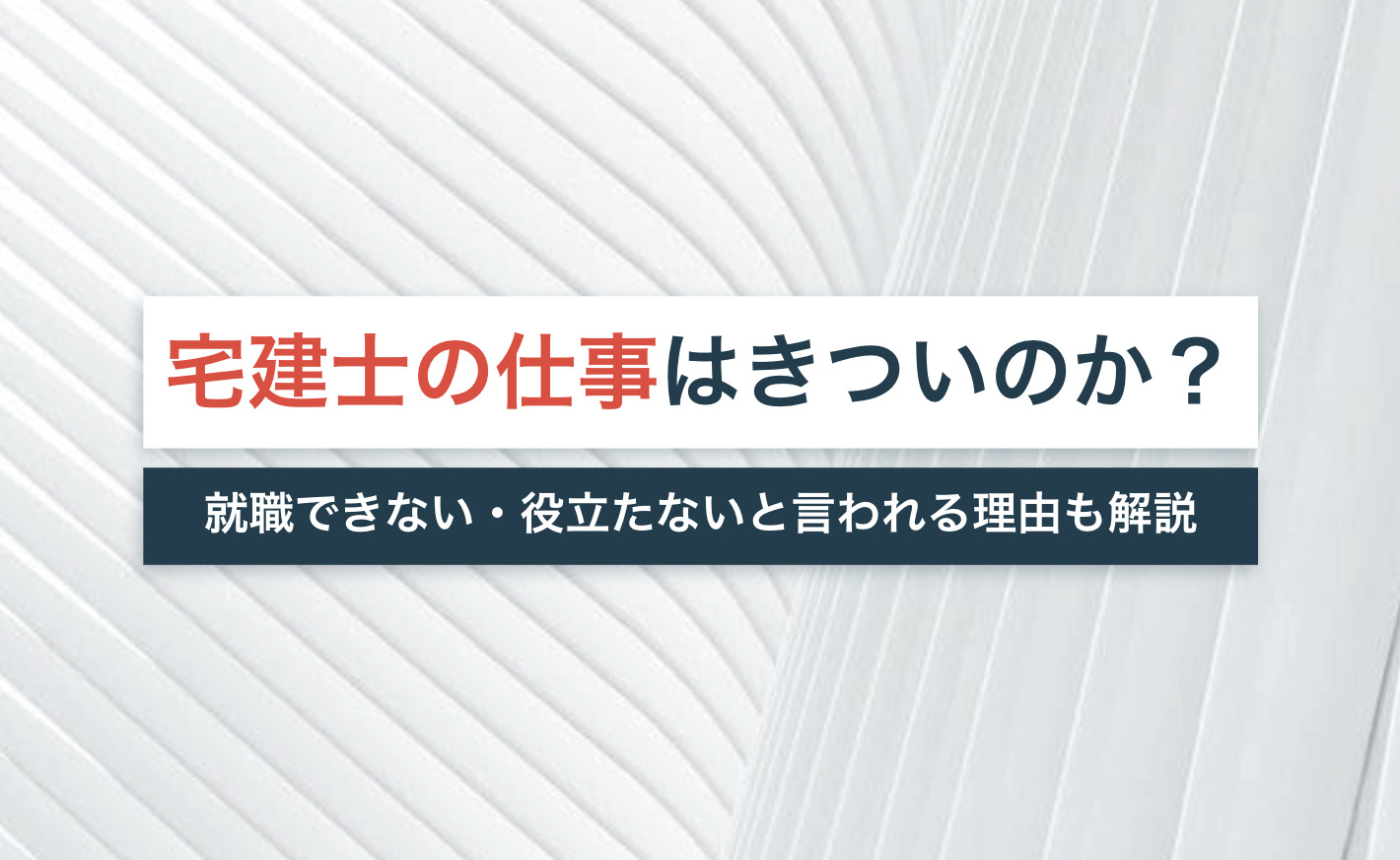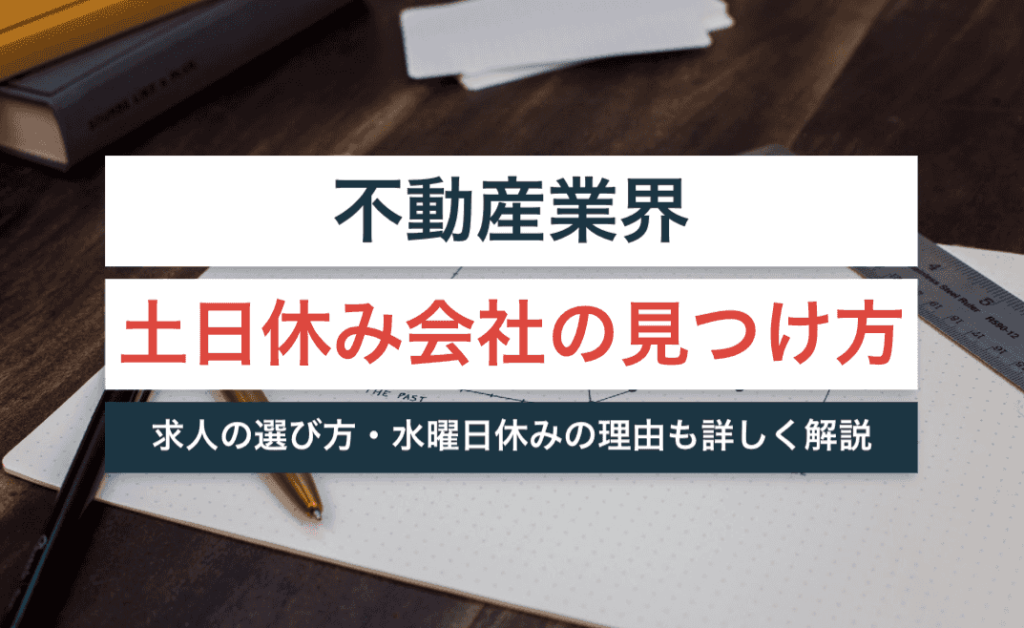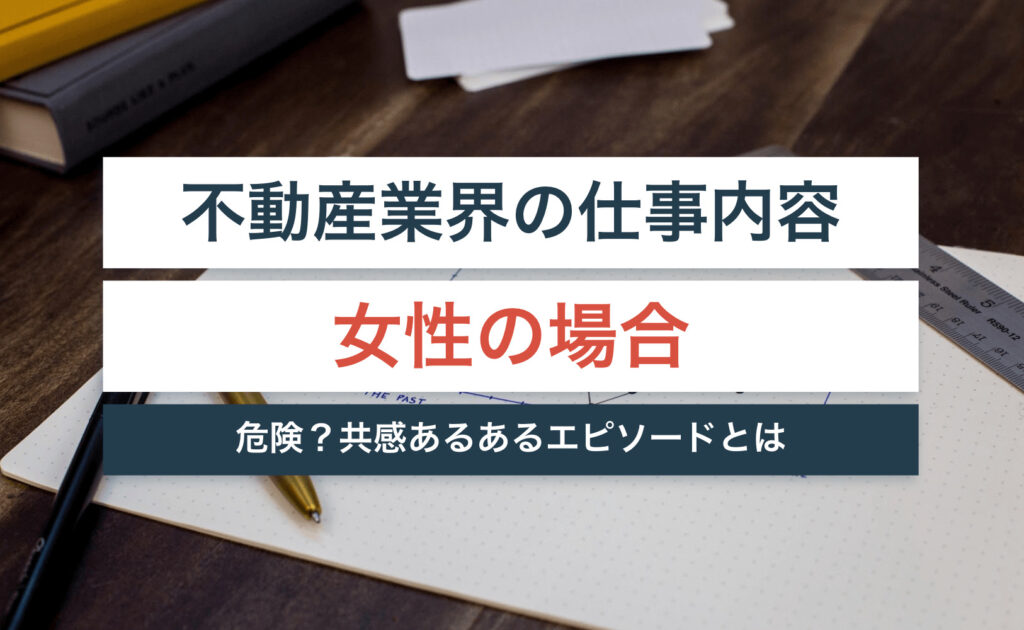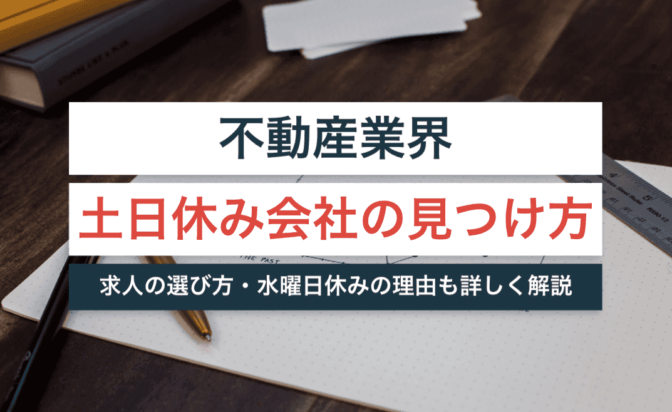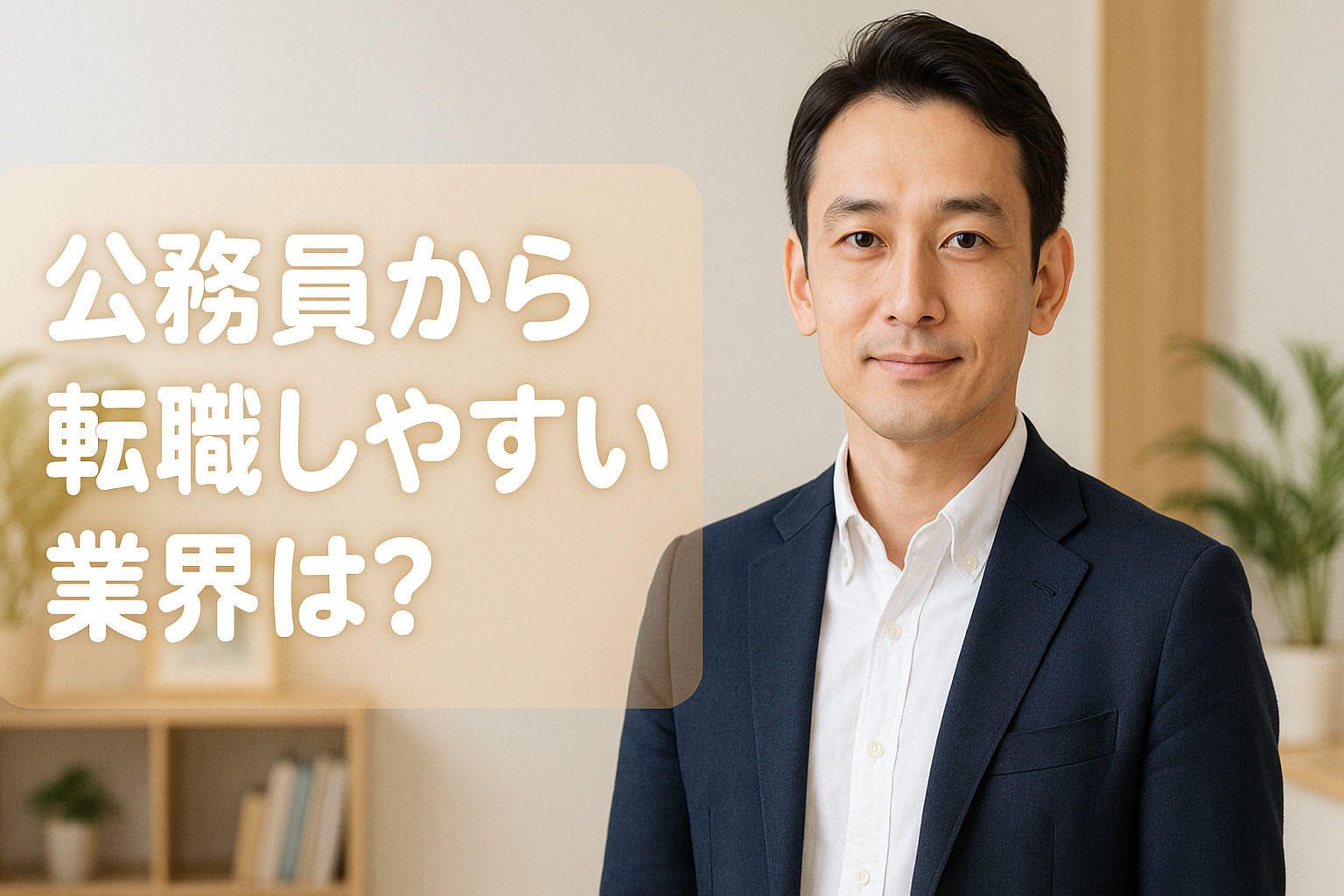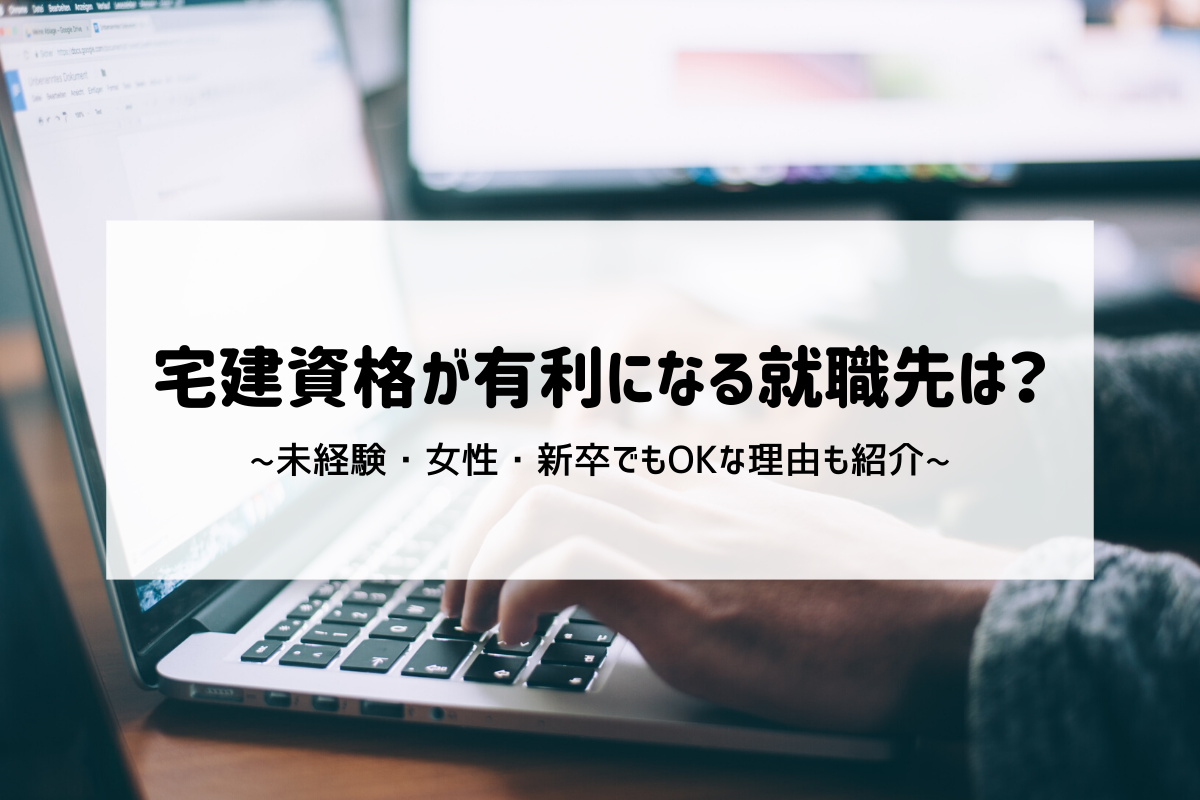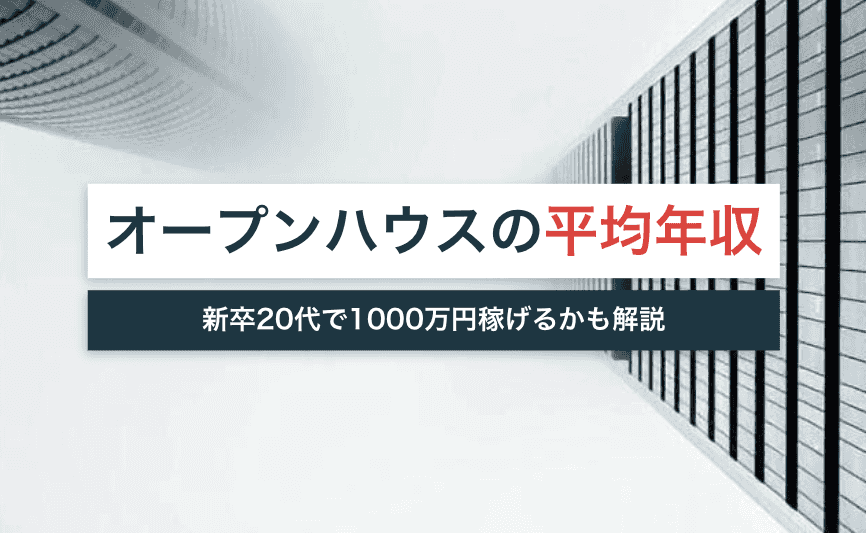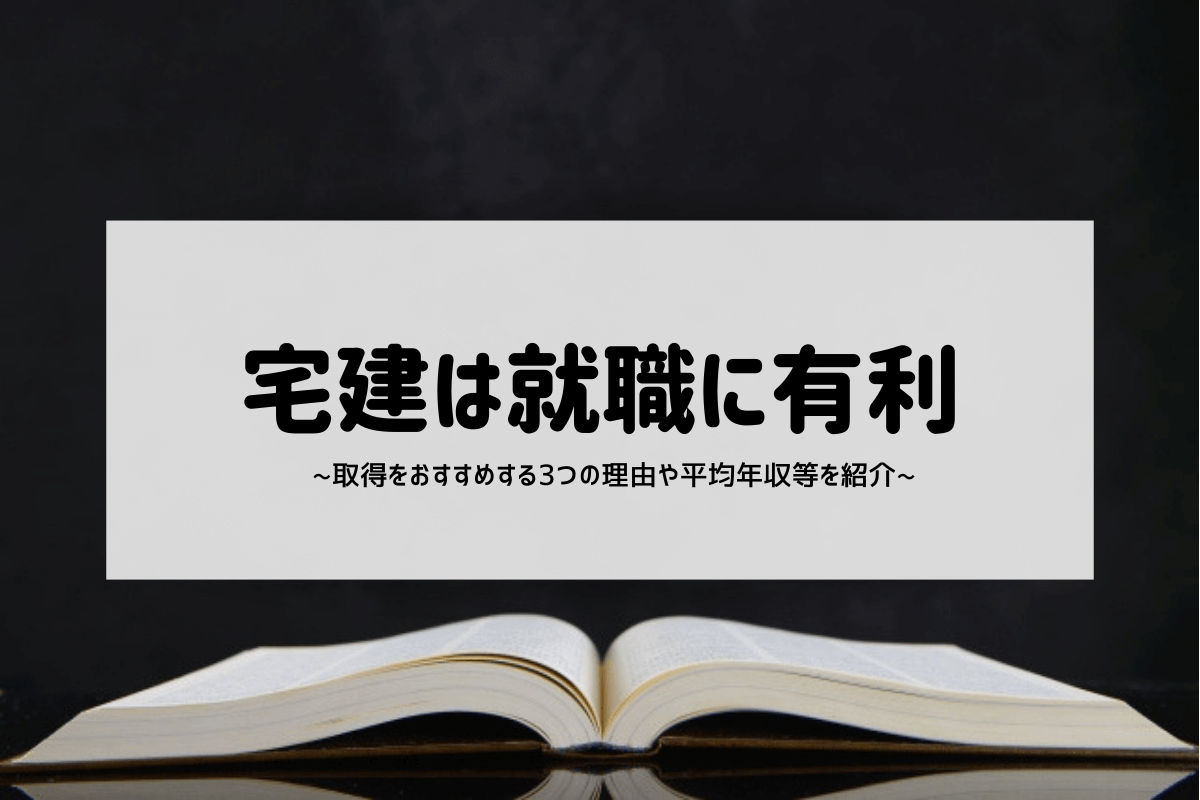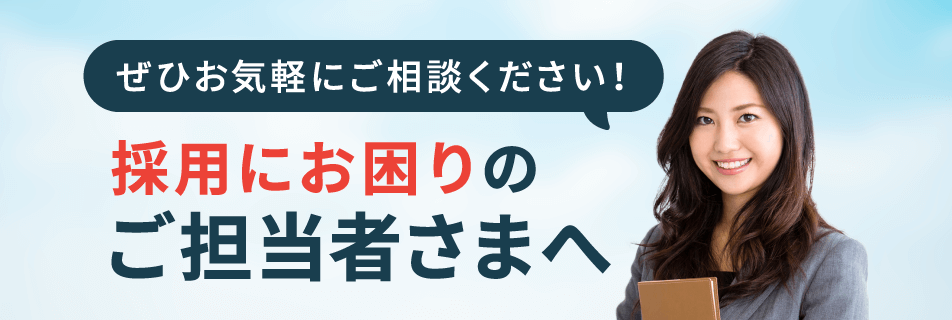不動産業界で転職をご検討の方!
宅建Jobに相談してみませんか?
※経験や資格は問いません。
「宅建士の仕事がないっていうのはほんとなの?」
「宅建の資格を持っていても、就職できないこともあるの?」
このような不安から宅建を受けるべきか悩んでいる人もいるのではないでしょうか。
結論から言いますと、宅建士の仕事はあります。
ただ、宅建は仕事がない・需要がない資格だと言われていることも事実です。
そこでこの記事では、仕事がないと言われる理由や宅建を使った就職について実際の転職事例を交えて詳しく解説していきます。
これから宅建士の資格を活かして働くことを検討している方はぜひ、参考にしてください!

この記事・サイトの監修者
棚田 健大郎
保有資格:宅地建物取引士、管理業務主任者、マンション管理士、賃貸不動産経営管理士、行政書士、FP2級など多数保有
不動産業界歴10年以上。元上場企業不動産会社エイブルの営業マン。3000人の社員の中で、仲介手数料売り上げ金額第1位となるトップセールスを記録。個人のYouTubeチャンネル“棚田行政書士の不動産大学”では、登録者数20万人以上。

この記事・サイトの監修者
棚田 健大郎
保有資格:宅地建物取引士、管理業務主任者、マンション管理士、賃貸不動産経営管理士、行政書士、FP2級など多数保有
不動産業界歴10年以上。元上場企業不動産会社エイブルの営業マン。3000人の社員の中で、仲介手数料売り上げ金額第1位となるトップセールスを記録。個人のYouTubeチャンネル“棚田行政書士の不動産大学”では、登録者数20万人以上。
1.宅建士は仕事がないと言われる理由
宅建士は仕事がないと言われている理由はいったい何でしょうか?
ここでは、その理由を3つご紹介します。
- 宅建必須の求人は多くても2割程度だから
- 不動産業界は資格より営業能力が問われるから
- 資格保有者が多く代わりが効くから
宅建必須の求人は多くても2割程度だから
宅建士は仕事がないと言われる理由の一つは、宅建を必須としている求人がそこまで多くないからです。
不動産業界特化の宅建Jobエージェントが保有する求人のうち、宅建士必須の求人の割合は1割強、多くて2割程度で、残りの8割以上は宅建がなくても応募ができるものです。
総合エージェント大手のリクルートエージェントの公開求人でも、不動産系の求人36,565件のうち宅建必須の求人は5,737件で、割合で言うとこちらも15%程度と、それほど違いはありません。
このように、宅建との親和性が最も高い不動産業界ですら宅建を必須としている求人はそこまで多くなく、宅建を取っても仕事がないと言われる理由の一つになっています。
※詳しくはこちらの動画をご覧ください
不動産業界は資格より営業能力が問われるから
営業職ではどの業界でもそうですが、資格を所持していることよりも、営業成績が良い方が大切にされることは言うまでもありません。
それに、不動産営業は宅建を持っていないと働けないわけでもありません。(一部重説などの独占業務は制限されます。)
そのため、全く売上を上げない宅建士よりも、売上で会社に貢献してくれる宅建なし営業マンの方が、会社にとってはありがたい存在なわけです。
そして、不動産業界には宅建資格なしでも会社から大切にされている有能な人材が沢山いることも事実です。
このように宅建はただ持っているだけではそこまで重宝されることもないため、仕事がないと言われることがあります。
関連記事はこちら!
宅建は不動産営業に必須の資格?「必要・不要」それぞれの意見を詳しく紹介!
資格保有者が多く代わりが効くから
令和5年現在、宅建保有者は全国におよそ118万人もいます。
そして、宅建は毎年20万人ほどが受験する人気資格ですから、今後もその数は増加していくと思われます。
加えて最近は、「週末宅建士」という言葉がよく聞かれるようになるほど、宅建士をアルバイトで雇う企業もあります。
つまり会社側は、宅建士の人数は必置義務(従業員5人に1人)さえ満たしていれば、足りない宅建士の人手はアルバイトでもいいと考えている場合があるということです。
そのため、宅建を取ったからと言って正社員の仕事が確約されているというわけではないため、宅建士は仕事がないと言われてしまうんです。
【補足データ】転職成功者の宅建取得状況を解説
この章では「宅建士は仕事がないらしい」という声や、そこから派生する「不動産業界で宅建は本当に必要なのか?」という疑問を整理してきました。
とはいいつつ、「業界未経験OKと謳いつつ結局は宅建を持っていないと落とされる」と不安に感じる方は多いのではないでしょうか?
そこで、今回は2024/4~2025/3間に宅建Jobエージェントを利用して、不動産業界の企業の内定を獲得した人の宅建保有状況を調べてみました。
すると、業界未経験での転職の方でも転職の際に宅建を持っていたのはわずか26%という結果になりました。
言い換えれば4人中3人は資格なしでも内定を掴んでいるという結果です。
ただし、もちろん宅建に関する知識はあるにこしたことはないです。
なぜなら、たとえ資格自体は持っていなくても学習している事実や知識を身につけようとする姿勢自体は評価の対象となりますし、入社後には結局宅建取得が必要になる会社もあるためです。

次の章では、宅建士の仕事の将来性について解説していきます。
2.宅建士の仕事には将来性がある
冒頭でもお伝えした通り、宅建士の仕事はあります。
将来性のある資格でもあるため、取得して損することはありません。
ここではそう言える根拠を2つご紹介します。
- AIに仕事を奪われない
- 不動産需要はなくなることがない
AIに仕事を奪われない
宅建士には、宅地建物取引業法という法律で規定される独占業務があります。
- 重要事項説明
- 重要事項説明書面への記名・押印
- 契約書への記名・押印
これらの業務は、宅建を持っている人にしかできないため、AIが代替することはできません。
また、接客やクロージングの際に、現状AIではとても判断のつきにくい、「子どもが安全に通学できる環境」「風通しがよく湿気がこもらない」などの要望が出ることがあります。
このような問い合わせにどんな知見やトークで対応するかは、人間の営業の腕の見せどころとなります。
需要がなくなることはない
不動産業は経済の変化に合わせて、比較的短いスパンで景況が変動します。
しかし、住まいや暮らしの需要自体はあり続け、その総数に大きな変化はないともいえるのです。
たとえば今後、新規の住宅供給など一部の分野が不調になったとしても、賃貸業や空き家利用などが形を変えて顧客ニーズを補完したりします。
リースバックやリバースモーゲージ、サブリースなど新しく台頭してくる分野も登場します。
これらはすべて不動産業がカバーする範囲なのです。
また、宅建士の資格を活かせるのは不動産業だけではありません。
後述しますが不動産賃貸業(いわゆる大家さん)、金融業、投資・資産運用コンサルタント、企業の資産管理部門、自治体(地方公務員)など、様々な業種にわたります。
関連記事はこちら!
宅建は就職に有利!取得をおすすめする3つの理由や平均年収等を紹介
不動産業以外でも宅建資格を活かせる?! 転職に有利な仕事6選を紹介!
宅建を活かして転職したい方へ
宅建資格を活かして働きたいと考えている方は、宅建Jobエージェントまでご相談をしてみてはいかがでしょうか?
宅建Jobエージェントは不動産業界に特化した転職エージェントで、条件の良い非公開求人をたくさん保有しています。
転職成功まで完全無料でサポートします。ぜひ、お気軽にお問い合わせください。
無料相談してみる >>> こちらから
3.宅建士の仕事に関するよくある質問
ここでは、宅建の仕事に関してよくある質問に、宅建Jobエージェントの転職事例を参考にお答えします。
利用者数・転職支援実績No.1※
※2024 年 6 月期_指定領域における市場調査|調査機関:日本マーケティングリサーチ機構
▽宅建Jobエージェントの評判はこちらから
宅建を取得しても就職できない?
宅建を取得しても役に立たないという人がいますが、それはありえません。
不動産業界では、資格手当として宅建保持者にお金を払っている企業が多数ありますから、収入面でも潤います。
就職においては、確かに宅建を持っているだけでは就職に必ず成功するという訳ではありません。
不動産業界では宅建士しかできない独占業務があるので、採用される確率はかなり高いと言えるでしょう。
なお、不動産業を営む際は、前述のようにひとつの事務所において「業務に従事する者」5人につき1人以上の割合で、専任の宅建士の設置が義務付けられています。
この要件が満たされていないと営業ができなくなるため、宅建の資格を持っている社員は必要とされる存在です。
転職事例①(20代/女性/未経験)前職:美容クリニック→不動産売買仲介営業
稼ぎたいという理由から、不動産営業への転職を目指して宅建の勉強を始め、見事一発合格。
11月下旬の合格発表直後から転職活動を始め、約1か月ほどで大手不動産会社の売買仲介営業職で内定を獲得。
無料転職相談してみる >>> こちらから
関連記事はこちら!
宅建士の仕事内容メインは3つ!給料や就職・転職に有利な理由を解説
宅建取得者と営業経験者ではどちらが優遇される?
一概には比較できませんが、「売れるけど宅建なし」と「宅建あるけど売れない」なら、宅建なしの方が優遇されるといえます。
宅建業務は他の社員に任せれば良いため、会社としては売上を伸ばしてくれる社員の方が必要だからです。
前項で述べたように理想としては、「宅建士の資格を持っている凄腕の営業マン」ですが、重要事項の説明などだけなら宅建の資格を持っているパートの女性事務員でもできるので、営業スキルが高ければ問題ありません。
ただ、宅建資格を持っている方が、顧客に「不動産の専門家」としてアピールできる面もあるので、信用度が高まるというメリットがあります。
関連記事はこちら!
不動産営業は未経験でも転職可能?他業界の転職先も多い?【志望動機の書き方も解説】
40代、50代、60代で宅建をとって再就職はきつい?
不動産業界は他業種と比較すると、人の出入りが激しい業界です。
若ければ未経験でも将来性を買われて採用されることも多く、40代までなら何とか可能といえるでしょう。
不動産の仕事に携わりたいと考え、宅建を取得。
転職開始後、わずか2社目の面接で内定を獲得。営業未経験ながらも、独学で宅建に合格した意欲を高く評価されて、見事転職を成功させた。
また、50代や60代でも転職が不可能というわけではありません。
ただし、下記事例のように、即戦力になれるような経験がないと厳しいという点は注意が必要です。
一身上の都合で離職していたが、3年間の実務経験を活かして不動産会社に転職。転職後は宅建士の独占業務である契約業務を担当。宅建資格と実務経験を活かして即戦力として活躍中。
無料転職相談してみる >>> こちらから
関連記事はこちら!
宅建は転職に有利!40代までなら未経験可能な理由と転職先を紹介!
女性が宅建の仕事をするのはきつい?
不動産業界での仕事は、女性だからきついということはありません。
性別に関係なく、成果を上げるという点では男性も女性もやることは同じだからです。
ただ、男性中心の社会のため女性は少数派であることが多く、心理的にきついと感じる人もいるでしょう。
どちらかというと事務職はノルマもないため、営業職のように過剰なストレスを溜め込むことはないようです。
とはいえ、女性でも売買営業としてバリバリ働き、成果を上げている人もたくさんいるので、自分の適性に合った職種を選ぶのをオススメします。
関連記事はこちら!
女性宅建士の仕事はきつい?男女の年収差・働く現実を詳しく解説不動産営業事務の仕事内容は?未経験女性にもおすすめな3つの理由
どんな仕事で活かせる?
宅建の資格が活かせる仕事の代表的なものは以下です。
| 不動産業 | 仲介業・賃貸業・デベロッパー・ハウスメーカーほか |
|---|---|
| 金融機関 | 銀行、保険会社等で融資、担保審査業務ほか |
| 投資・資産運用コンサルタント | 不動産投資、小口債権、資産運用コンサルタント |
| 自治体(都市計画・開発など) | 公務員として都市計画、開発関連業務 |
不動産業では、必置義務や独占業務のある仲介だけでなく、ほとんどの職種で宅建の資格や知識を活かすことができます。
稼ぐということを基準にすると、営業スキル+宅建資格というのがもっとも強く、それに準じて宅建+投資コンサルスキルが有利と言えるでしょう。
そのほか、金融や公務員を志向する際に、専門分野にできる強みとして宅建士を取得しておくと、安定した地位や収入を得やすくなります。
ダブルライセンスはオススメできる?
上記の金融や公務員のケースに近いのですが、不動産業で宅建以外の資格をもつダブルライセンスで、宅建資格をさらに活用することができます。
管理業務主任者は単独でもマンション管理会社の求人があり、宅建にとっては管理組合を顧客としたフロント業務の方向に仕事を拡げる効果があります。
マンション管理士は現状では求人が少ないですが、住人の高齢化や建物の老朽化により、今後ニーズが増える可能性があります。
賃貸不動産経営管理士も、今後5年~10年で、宅建士との組み合わせで需要が高まると噂されています。
その他仲介や投資で、顧客の財政状況を把握して行うアドバイスや、自ら独立して経営に乗り出す基礎のために、宅建以外にFPや簿記などを取得する人も多いです。
4.宅建士の仕事がきついと言われる理由
「宅建士はきついからやめとけ」と言われることもあります。
宅建がきついというより営業のノルマや長時間労働など、不動産業界特有のつらさの印象が強く、決して宅建士自体がきつい訳ではありません。
ただし、きついと言われる理由もしっかりあるので、ここで解説していきましょう。
任される業務の幅が広い
宅建士は営業や事務などの通常業務に加えて、宅建士にしかできない独占業務を行えます。
したがって、任される業務の幅が広いため仕事が多いといえるでしょう。宅建士が行える独占業務には以下の3つがあります。
- 重要事項説明
不動産の売買や賃貸借に関する契約を締結する際に、売主や貸主は契約に関する様々な重要事項を買主や借主に対し、契約締結前に説明する義務を負っています。不動産取引では高額な金銭や権利の受け渡しがされるため、後日トラブルが発生することのないようにしっかりと契約内容を買主や借主に確認してもらうのです。説明をしないまま契約してしまった場合、宅建業者は罰金を払わなければなりません。 - 重要事項(35条書面)への記名・押印
不動産契約に関する重要事項はたくさんあり広範囲にわたります。したがって、事前に説明書を作成して書面を見ながらお客様に宅建士が口頭で説明を行います。説明した後は宅建士が記名・押印をし、買主や借主に交付します。 - 契約書(37条書面)への記名・押印
契約書にも宅建士の記名・押印が必要です。重要事項説明や説明書の交付が済ませた後、契約内容に間違いがないことを確認したうえで契約書へ記名・押印をします。
クレーム対応が多い
不動産業界でクレームが発生するのは日常茶飯事です。
不動産の取引には高額な資金や権利の移転などが絡むため、お客様もシビアになります。ゆえに、クレームも多くなりがちです。
また、不動産取引の仕組みは非常に複雑であり、素人であるお客様には簡単に理解できない点も少なくありません。
お客様にはきちんと説明したつもりでも、違うように解釈している場合もあるため、行き違いが生じることもあるのです。
営業マンの言葉が足りないと顧客が自分に都合の良いように解釈する場合もあるので、しっかりと説明をしておきましょう。
顧客からクレームがあったときにはスピーディーに対応し、親身になってコミュニケーションを取ることが必要です。こまめに連絡をしながらクレーム内容に的確に対応することで、顧客から信頼されるようになります。
関連記事はこちら!
不動産業界はクレームが多い?トラブル事例や対応方法を詳しくご紹介!
離職率が高い
厚生労働省が調査した「令和4年 雇用動向調査結果の概要」によると、不動産業および物品賃貸業の離職率は13.8%でした。
不動産業は全産業15種類のうち、離職率の高さでは6位という結果です。
飛びぬけて高いわけではありませんが離職率は高い方であるといえます。
関連記事はこちら!
不動産業界の離職率は高い?低い?職種ごとに違う理由を解説
労働時間が長い
2019年4月から「働き方改革関連法」が施行され、不動産業界でも時短勤務やテレワークの活用などで労働時間の見直しを進めています。
そのような取り組みもあり、不動産業界は以前より残業時間がかなり減少しました。とはいえ、他業種と比べるとまだまだ長い方であり、サービス残業も多い傾向となっています。
賃貸営業の場合、進学や就職、転勤などに伴う部屋探しが集中する年度末前後は繁忙期のため、接客業務や契約業務に追われることになります。
人手が足りないと休日でも出勤したり、夜遅くまで働いたりすることも少なくありません。
投資マンションなどを扱う売買営業は、お客様の都合により商談の日時が決まるため、自分の予定は後回しになってしまいます。
暇な時期は休日もしっかり取れて、遅くまで仕事をすることもありませんが、繁忙期には残業が増えたり休日出勤になったりする場合が多い業界です。
関連記事はこちら!
不動産業界で残業が多い理由は?残業代についても詳しく解説!【やめとけ】不動産事務はきつい?実は暇?実態を分かりやすく解説!
厳しいノルマに追われる
不動産業界の営業職は、特にノルマが厳しいことで知られています。
特に売買の営業は給料のシステムがインセンティブ制のため、成果を上げれば高収入を得られますが、売れないと薄給になるのがデメリットです。
厳しいノルマに常に追われることになり、神経が休まる暇はありません。数字を達成できないと上司から追い込みをかけられるため、タフな神経の持ち主でないと務まらないでしょう。
関連記事はこちら!
【図解】不動産営業ノルマはどのくらい?達成がきつい理由と売上目安を紹介
5.「宅建 仕事ない」のまとめ
宅建の資格を活かせる仕事は幅広くあり、不動産の専門家としての知識を存分に発揮することが可能です。
ぜひ、宅建の資格を活かして仕事面で役立ててください。
宅建の資格を活かせる仕事にご興味がある方へ!
宅建の資格を活かせる仕事にご興味がある方は、宅建Jobエージェントまでご相談をしてみてはいかがでしょうか?
宅建Jobエージェントは不動産に特化した転職エージェントで、信頼できるきちんとした企業の求人を多数保有しております。
プロのキャリアアドバイザーが親身になって、面接対策や志望動機の書き方まサポートしますので、不動産業界は初めてという方でもご心配には及びません。
登録やご相談は一切無料ですので、ぜひ、お気軽にお問い合わせください。
親身になって、
あなたの転職をサポートします!
キャリアアドバイザーへの
無料相談はこちらから!
不動産業界で転職をご検討の方!
宅建Jobに相談してみませんか?
※経験や資格は問いません。